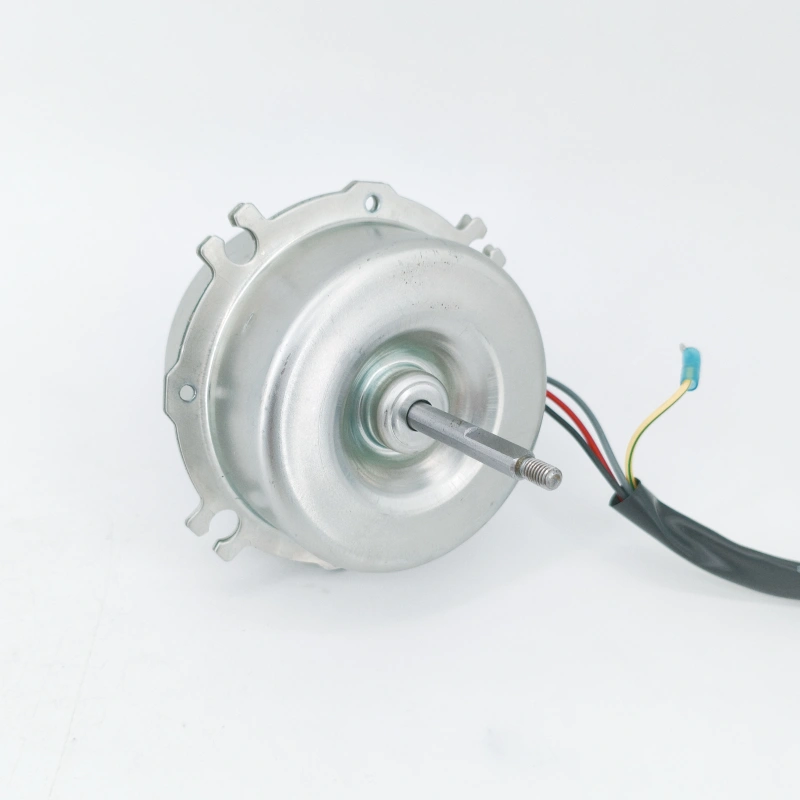ACモーターは、構造がシンプルで信頼性が高く、コストが低いという利点から、工業生産、家電製品などの分野で広く使用されています。速度は、電源周波数、モーターの極数、および滑り率(式:n = 60 f / p(1-s)、ここでnは速度、fは電源周波数、pは極数、sは滑り率)によって影響を受けます。この原理に基づいて、一般的な速度制御方法は以下のカテゴリに分類できます。
1、電力周波数制御に基づく制御方法:可変周波数速度制御
可変周波数速度制御は、現在、交流モータの速度制御において最も広く使用されている高精度な制御方法です。その核心は、入力モータの電源周波数を変化させることで、精密な速度調整を実現することです。
動作原理:周波数変換器を使用して、AC電源(220V / 50Hz、380V / 50Hzなど)を調整可能な周波数のAC電源に変換し、モーターの特性に応じて電圧を合わせ(通常はモーターの磁気回路の飽和を回避するために「定電圧/周波数比」の原則に従います)、モーターの同期速度を変更します。
特徴: 広い速度範囲 (0 から定格速度まで、または定格速度を超えて動作できます)、高精度 (速度誤差を 0.5% 以内に制御できます)、低エネルギー消費 (低速動作中でもモーターの効率は高く維持されます)、起動時にサージ電流が発生せず、モーターと負荷機器を効果的に保護します。
2、モータ極数調整に基づく制御方法:可変極速度制御
可変極速度制御は、固定子巻線の接続を変更することでモーターの磁極数 (p) を調整し、同期速度を変更する段階的な速度制御方法です。
動作原理:モーターの固定子巻線は特殊なタップまたはスイッチング構造を採用し、巻線の接続方法は接触器によって切り替えられます(スター/トライアングル変換、ダブルスター/トライアングル変換など)。これにより、磁極の数は指数関数的に変化します(2極から4極など)。それに応じて同期速度が半分に低下します(50Hz電源周波数で3000r/minから1500r/minなど)。
特徴: 構造がシンプルで、コストが低く、操作が簡単で、速度調整時にモーターの効率は基本的に変わりませんが、速度調整レベルが限られています (通常、2 極 / 4 極 / 6 極切り替えなど、速度調整は 2 ~ 3 レベルのみ)。連続的な速度調整ができず、切り替え時に速度ショックが発生する可能性があります。
3、スリップ調整に基づく制御方法
スリップ率(s)は、モータの実速度と同期速度の差と同期速度の比です。スリップ率を変化させることで、交流モータの速度制御が可能になります。一般的な方法としては、直列抵抗速度制御、直列段速度制御、電圧制御などがあります。
直列抵抗速度制御(巻線ローター非同期モーターにのみ適用)
動作原理:巻線型非同期モータのロータ回路には、可変抵抗器が直列に接続されています。抵抗値を大きくすると、スリップ率が増加し、モータの実速度が低下します(抵抗値が大きいほど、回転速度は低くなります)。
特徴: 構造が簡単で、コストが低いですが、エネルギー消費量が多く(直列抵抗により大量のジュール熱が発生し、エネルギー損失が深刻です)、速度調整精度が低く(負荷の変化により速度が大きく変動します)、低速運転時にモーター効率が大幅に低下します。